Asagi's Art News
命を見つめる ~ 生誕100年 靉光展 ― 2007年04月07日 22時30分09秒
ソメイヨシノが花吹雪を起こし、そろそろ盛り上っていた東京のお花見もフィナーレを向かえつつあります。日本のシュルレアリストとして評価され、戦争によって命を落とした画家、靉光の展覧会がひっそりとはじまりました。
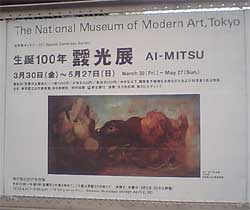
テレビの美の巨人たちでも紹介された『眼のある風景』は、画家の心に秘めた何かを語っているようです。絵の中央にある目がとても印象的で、少しさびしげ感じもしてきます。
現世と彼の世とが混ざり合う不思議な世界が画面に広がります。鳥や魚は、血の気が無くなりやがて乾いていく。すべてが赤茶けて錆びていくような感じがします。画家は、無の世界を描こうとしていたのでしょうか?
もちろん、最初から難しい世界を描いていたわけでもなく、初期の作品には、ゴッホやルオーを意識した作品が多く見られます。その中にロウ画と言う作品がいくつかありました。
ロウ画とは、溶かしたロウやクレヨンに岩彩(岩絵具ようなもの)を混ぜ絵具として使ったものです。出来上がった作品は、独特の光沢があり、作品に深みを持たせるように思います。彼が描いたロウ画ですが、あまり大きくはありません。だからでしょうか、コンパクトでお洒落な感じがしました。
特に気に入ったのは、ポスターにもなっている『編み物をする女』です。この作品のモデルは、彼の奥さんであるキヱ夫人です。物静かに編み物をする姿に微笑ましい愛情を感じます。また、技法的にも凝っていて、背景などは琳派的なものを感じます。

靉光「編み物をする女、1934」
温かみを感じるのは、彼にとってもいちばん幸せだった頃の作品だったからだと思います。以後の作品が渋く重たいためでしょうか、ホッとする一枚のような気がします。そして、命を考える原点だったかもしれません。
最後に彼の最後の作品となる自画像が3点あります。徴兵される前の作品となるのですが、とても感慨深い表情をしています。戦争が始まる前から命について考え作品を作ってきた。そして、明日には自分の命が消えるかもしれない。そんな表情のように思いました。
※東京国立近代美術館
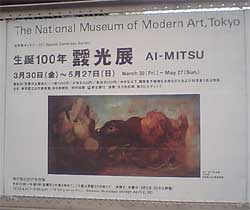
テレビの美の巨人たちでも紹介された『眼のある風景』は、画家の心に秘めた何かを語っているようです。絵の中央にある目がとても印象的で、少しさびしげ感じもしてきます。
現世と彼の世とが混ざり合う不思議な世界が画面に広がります。鳥や魚は、血の気が無くなりやがて乾いていく。すべてが赤茶けて錆びていくような感じがします。画家は、無の世界を描こうとしていたのでしょうか?
もちろん、最初から難しい世界を描いていたわけでもなく、初期の作品には、ゴッホやルオーを意識した作品が多く見られます。その中にロウ画と言う作品がいくつかありました。
ロウ画とは、溶かしたロウやクレヨンに岩彩(岩絵具ようなもの)を混ぜ絵具として使ったものです。出来上がった作品は、独特の光沢があり、作品に深みを持たせるように思います。彼が描いたロウ画ですが、あまり大きくはありません。だからでしょうか、コンパクトでお洒落な感じがしました。
特に気に入ったのは、ポスターにもなっている『編み物をする女』です。この作品のモデルは、彼の奥さんであるキヱ夫人です。物静かに編み物をする姿に微笑ましい愛情を感じます。また、技法的にも凝っていて、背景などは琳派的なものを感じます。

靉光「編み物をする女、1934」
温かみを感じるのは、彼にとってもいちばん幸せだった頃の作品だったからだと思います。以後の作品が渋く重たいためでしょうか、ホッとする一枚のような気がします。そして、命を考える原点だったかもしれません。
最後に彼の最後の作品となる自画像が3点あります。徴兵される前の作品となるのですが、とても感慨深い表情をしています。戦争が始まる前から命について考え作品を作ってきた。そして、明日には自分の命が消えるかもしれない。そんな表情のように思いました。
※東京国立近代美術館
コメント
_ とら ― 2007年04月09日 21時33分35秒
靉光の展覧会は本当に「ひっそりと」始まりましたね。わたしのお気に入りも「編み物をする女」がベストでした。
_ あさぎ ― 2007年04月10日 01時02分58秒
>とらさん
こんばんは、千鳥が淵の桜も見納めですね。
靉光展は、私の通っているデッサンの先生もお勧めの展覧会だったので、とても楽しみにしていました。申し訳ないと思っているのですが、期待以上に良い展覧会でした。
こんばんは、千鳥が淵の桜も見納めですね。
靉光展は、私の通っているデッサンの先生もお勧めの展覧会だったので、とても楽しみにしていました。申し訳ないと思っているのですが、期待以上に良い展覧会でした。
_ Tak ― 2007年04月15日 23時07分45秒
こんばんは。
桜も散ってしまいました。。。
この展覧会もっと注目されてもよいと思います。
桜も散ってしまいました。。。
この展覧会もっと注目されてもよいと思います。
_ あさぎ ― 2007年04月16日 00時26分36秒
>Takさん
こんばんは、コメント&TBありがとうございます。
国立近代らしい画家の一生を深く追求する良い展覧会ですね。たしかに注目度という点では、いまひとつですがたくさんの人に見て欲しい作品がたくさんあったように思います。
こんばんは、コメント&TBありがとうございます。
国立近代らしい画家の一生を深く追求する良い展覧会ですね。たしかに注目度という点では、いまひとつですがたくさんの人に見て欲しい作品がたくさんあったように思います。
_ 一村雨 ― 2007年05月16日 05時13分21秒
やっと見てきました。
私も初期のロウ画の作品、初めて知ったのですが、
たいへん気に入りました。
そうなんですよね。靉光にとっていちばん落ち着いた
いい時代だったからなんですよね。
私も初期のロウ画の作品、初めて知ったのですが、
たいへん気に入りました。
そうなんですよね。靉光にとっていちばん落ち着いた
いい時代だったからなんですよね。
_ あさぎ ― 2007年05月17日 23時43分20秒
>一村雨さん
こんばんは、そろそろ靉光展も終りに近づいてきましたね。いろいろなところで静かに注目されて、まだまだ知らないすごい画家がたくさんいると思いました。良い展覧会でした。
こんばんは、そろそろ靉光展も終りに近づいてきましたね。いろいろなところで静かに注目されて、まだまだ知らないすごい画家がたくさんいると思いました。良い展覧会でした。
トラックバック
_ Art & Bell by Tora - 2007年04月09日 21時34分56秒
半蔵門から桜満開の千鳥が淵を見ながら九段下へと散歩した。暖かく良い日和。
そして今日は、東京国立近代美術館で開かれる「生誕100年靉光展」の初日である。 靉光は第二次大戦で召集され、39歳で戦病死するまで、独特な画風のため画壇の主流には属さなかった。このことから彼は「異端の画家」と呼ばれたり、戦時中多くの画家が戦争を讃えたり、国民の戦意高揚を狙った「戦争画」を描いた中にあって、戦争画を一枚も遺さなかったことから、「抵抗の画家」とか「暗い谷間の画家」とも呼ばれている。
靉光の作品は、有名な《眼のある風景》や《自画像》など何点か見ているが、このように年代を追って彼の画歴を俯瞰した...
そして今日は、東京国立近代美術館で開かれる「生誕100年靉光展」の初日である。 靉光は第二次大戦で召集され、39歳で戦病死するまで、独特な画風のため画壇の主流には属さなかった。このことから彼は「異端の画家」と呼ばれたり、戦時中多くの画家が戦争を讃えたり、国民の戦意高揚を狙った「戦争画」を描いた中にあって、戦争画を一枚も遺さなかったことから、「抵抗の画家」とか「暗い谷間の画家」とも呼ばれている。
靉光の作品は、有名な《眼のある風景》や《自画像》など何点か見ているが、このように年代を追って彼の画歴を俯瞰した...
_ 紫式子日記 - 2007年04月10日 12時23分42秒
雨の竹橋、久しぶりに空いている美術館。
ていうか美術館自体久しぶり。
靉光は、1946年に38歳の若さで戦病死した画家。
実は知らない画家だったのだけれど、ポスターの絵の妙な薄暗さと、同時開催の「リアルのためのフィクション」展に惹かれ、参拝。
やはり東...
_ 弐代目・青い日記帳 - 2007年04月15日 23時06分44秒
東京国立近代美術館で開催中の
「生誕100年 靉光展」に行って来ました。
「靉光」(あいみつ、本名:石村日郎、1907-1946)
20代の頃に描いたデッサンには「靉川光郎」とサインされていました。
広島県出身の靉光は大正末に上京し池袋を拠点に独自の世界観を
様々な手法で表現した画家さんです。
39歳で夭折してしまったことに加え、
広島にあった作品が原子爆弾の被害に遭い
消失してしまったことなどの不運が重なり
現存する作品数が少ない画家さんだそうです。
詳しくはこちらのサイトで〜美の巨人たち〜
展覧会の構成は以下の通り。
第1章 初期作品
第2章 ライオン連作から《眼のある風景》へ
第3章 東洋画へのまなざし
第4章 自画像連作へ
「日本のシュールレアリスト」と呼ばれると伺っていましたが、
今回の回顧展を観て、それはあくまでもこの作家の一面でしか
ないことがよく分ったように思えます。
デッサン力や写実的な腕前は相当なものがあったことは
展示されている作品を観ればまさに一目瞭然です。
一種異様なまでに緻密な作品も数点観られます。
靉光の生まれ持った画才がいかに凄いものかは
既に10歳の頃にこの作品を描いたことからも理解できます。
父親を描いた作品です。ピカソもビックリ!。
これ10歳の時に描いたなんて…バカテクの持ち主です。
18歳で上京し、下宿生活をしながら「池袋モンパルナス」と呼ばれた
絵描き仲間と共に新たな境地を切り開こうと画業に打ち込みます。
↓の2枚の作品は共に1929年に描かれたものですが
西洋絵画の影響を強く受けていることが分ります。
それぞれ、誰の作風を意識しているかさえも。
「コミサ(洋傘による少女)」
↑これはルオーの影響を受けたのでしょうね。
「屋根の見える風景」
↑こちらはゴッホ。筆致がそっくりです。
天才はやはり何でも上手くこなすことが出来るものです。
次の日になるとガラリと違った画風になっていたこともあり
友人たちを驚かせたというエピソードまであるそうです。
「器用貧乏」という言葉がありますが、靉光もまた「天才貧乏」に
悩まされることになって行ったそうです。
あれだけ写実的に描けるのだから悩むことないのにな〜と思うのは
凡人の証。天才は更なる境地目指し常に高見を見据えているものです。
ロウやクレヨンを溶かし、岩彩と混ぜて描いた「ロウ画」は
そんな悩める天才画家が生み出した新たな技法のひとつです。
「編み物をする女」1934年
この頃、靉光は思い通りに絵が描けないと涙ながらに呟いていたそうです。
〜美の巨人たち〜では、チラシやポスターに用いられている代表作「眼のある風景」と上野公園でデッサンを重ねたライオンとの関わりを「説」として解説されていますが、今回の展覧会では「第2章 ライオン連作から《眼のある風景》へ」とし密接な関連が確かにあったのだと解説が展開されていました。
それは、技法を確立しようと悩んだ靉光が、「ライオン」という対象を深く観察しデッサンしていくうちにその内側に潜む本質を捉え思いのままキャンバスに表したのではないかということです。
テクニックに頼るのではなく、描く対象をとことん自分の目で追究する。
そんな態度の変化がもたらしたのが「眼のある風景」だとすると、
単にシュルレアリズムの画家とこの絵だけで判断してしまうのは性急なことです。
そのように考えるとふと皇居のお堀に咲く満開の桜をもし靉光が対象として捉え
深く深く見つめ、デッサンを重ねたとしたらもしや「屍体」が埋まっている!
のではないかと、梶井基次郎の想いと強くシンクロするように思えました。
(梶井基次郎「桜の樹の下には」)
美と醜、生と死。。。
「鳥」1942年
「眼のある風景」から数年後に描かれた作品です。
モディリアーニの目のような鳥と美しい花が独特な構図でまとめられています。
死んだ鳥と活ける花。
二つの相反する対象物が一枚の絵の中に座り宜しく収まっています。
生と死の境界線がないかの如く。
第二次大戦が激化し抽象画が取り締まりが厳しくなると
靉光が選んだモチーフは自分自身でした。
最後の展示室には三枚の自画像が並べて展示されてあります。(1943−44年)
三枚とも同じような姿勢の自画像です。
何ゆえこのようなポーズの作品を描いたのでしょう。
広い胸、太い首。
そして、その目は何を見つめているのでしょう。
その目の先にある対象物は一体……
思想的なものは私には感じられませんでした。
ただ画家として自分自身を描く対象として
その本質を見るべく目こ凝らしているように観えました。
この後、1944年5月に召集を受け中国へ送られ、
戦後間もなく発病し1945年1月上海で戦病死したそうです。
38歳という若さで。
自身を見据え見えた本質はやはり「死」だったのかもしれません。
それでは、「今日の一枚」
手向けに「花(アネモネ)」を。
お花見の喧騒もひと段落した頃かと思います。
「生誕100年 靉光展」お薦めできる展覧会です。是非。
以下へ巡回するそうです。
宮城県美術館 6月9日−7月29日
広島県立美術館 8月10日−10月8日
常設展のチケットでも観られる
「リアルのためのフィクション」(Fiction for the Real)展も開催中です!
おまけ:2月に常設展に展示されていた「眼のある風景」です。
この記事のURL
http://bluediary2.jugem.jp/?eid=974
「生誕100年 靉光展」に行って来ました。
「靉光」(あいみつ、本名:石村日郎、1907-1946)
20代の頃に描いたデッサンには「靉川光郎」とサインされていました。
広島県出身の靉光は大正末に上京し池袋を拠点に独自の世界観を
様々な手法で表現した画家さんです。
39歳で夭折してしまったことに加え、
広島にあった作品が原子爆弾の被害に遭い
消失してしまったことなどの不運が重なり
現存する作品数が少ない画家さんだそうです。
詳しくはこちらのサイトで〜美の巨人たち〜
展覧会の構成は以下の通り。
第1章 初期作品
第2章 ライオン連作から《眼のある風景》へ
第3章 東洋画へのまなざし
第4章 自画像連作へ
「日本のシュールレアリスト」と呼ばれると伺っていましたが、
今回の回顧展を観て、それはあくまでもこの作家の一面でしか
ないことがよく分ったように思えます。
デッサン力や写実的な腕前は相当なものがあったことは
展示されている作品を観ればまさに一目瞭然です。
一種異様なまでに緻密な作品も数点観られます。
靉光の生まれ持った画才がいかに凄いものかは
既に10歳の頃にこの作品を描いたことからも理解できます。
父親を描いた作品です。ピカソもビックリ!。
これ10歳の時に描いたなんて…バカテクの持ち主です。
18歳で上京し、下宿生活をしながら「池袋モンパルナス」と呼ばれた
絵描き仲間と共に新たな境地を切り開こうと画業に打ち込みます。
↓の2枚の作品は共に1929年に描かれたものですが
西洋絵画の影響を強く受けていることが分ります。
それぞれ、誰の作風を意識しているかさえも。
「コミサ(洋傘による少女)」
↑これはルオーの影響を受けたのでしょうね。
「屋根の見える風景」
↑こちらはゴッホ。筆致がそっくりです。
天才はやはり何でも上手くこなすことが出来るものです。
次の日になるとガラリと違った画風になっていたこともあり
友人たちを驚かせたというエピソードまであるそうです。
「器用貧乏」という言葉がありますが、靉光もまた「天才貧乏」に
悩まされることになって行ったそうです。
あれだけ写実的に描けるのだから悩むことないのにな〜と思うのは
凡人の証。天才は更なる境地目指し常に高見を見据えているものです。
ロウやクレヨンを溶かし、岩彩と混ぜて描いた「ロウ画」は
そんな悩める天才画家が生み出した新たな技法のひとつです。
「編み物をする女」1934年
この頃、靉光は思い通りに絵が描けないと涙ながらに呟いていたそうです。
〜美の巨人たち〜では、チラシやポスターに用いられている代表作「眼のある風景」と上野公園でデッサンを重ねたライオンとの関わりを「説」として解説されていますが、今回の展覧会では「第2章 ライオン連作から《眼のある風景》へ」とし密接な関連が確かにあったのだと解説が展開されていました。
それは、技法を確立しようと悩んだ靉光が、「ライオン」という対象を深く観察しデッサンしていくうちにその内側に潜む本質を捉え思いのままキャンバスに表したのではないかということです。
テクニックに頼るのではなく、描く対象をとことん自分の目で追究する。
そんな態度の変化がもたらしたのが「眼のある風景」だとすると、
単にシュルレアリズムの画家とこの絵だけで判断してしまうのは性急なことです。
そのように考えるとふと皇居のお堀に咲く満開の桜をもし靉光が対象として捉え
深く深く見つめ、デッサンを重ねたとしたらもしや「屍体」が埋まっている!
のではないかと、梶井基次郎の想いと強くシンクロするように思えました。
(梶井基次郎「桜の樹の下には」)
美と醜、生と死。。。
「鳥」1942年
「眼のある風景」から数年後に描かれた作品です。
モディリアーニの目のような鳥と美しい花が独特な構図でまとめられています。
死んだ鳥と活ける花。
二つの相反する対象物が一枚の絵の中に座り宜しく収まっています。
生と死の境界線がないかの如く。
第二次大戦が激化し抽象画が取り締まりが厳しくなると
靉光が選んだモチーフは自分自身でした。
最後の展示室には三枚の自画像が並べて展示されてあります。(1943−44年)
三枚とも同じような姿勢の自画像です。
何ゆえこのようなポーズの作品を描いたのでしょう。
広い胸、太い首。
そして、その目は何を見つめているのでしょう。
その目の先にある対象物は一体……
思想的なものは私には感じられませんでした。
ただ画家として自分自身を描く対象として
その本質を見るべく目こ凝らしているように観えました。
この後、1944年5月に召集を受け中国へ送られ、
戦後間もなく発病し1945年1月上海で戦病死したそうです。
38歳という若さで。
自身を見据え見えた本質はやはり「死」だったのかもしれません。
それでは、「今日の一枚」
手向けに「花(アネモネ)」を。
お花見の喧騒もひと段落した頃かと思います。
「生誕100年 靉光展」お薦めできる展覧会です。是非。
以下へ巡回するそうです。
宮城県美術館 6月9日−7月29日
広島県立美術館 8月10日−10月8日
常設展のチケットでも観られる
「リアルのためのフィクション」(Fiction for the Real)展も開催中です!
おまけ:2月に常設展に展示されていた「眼のある風景」です。
この記事のURL
http://bluediary2.jugem.jp/?eid=974
_ 徒然なるまままに - 2007年04月21日 18時11分32秒
生誕100年 靉光展
2007年3月30日から5月27日
東京国立近代美術館
靉光(本名:石村日郎、1907-1946)(AI-MITSU)の生誕100年を記念する展覧会。
いつも常設展に展示されている《眼のある風景》1938年を見て、強烈な印象を受けながら何を描いているのだろうと、不気味に思っていた。
概要で、「1924(大正13)年に上京し、中村不折らが指導する太平洋画会研究所に通うようになる」とあった。一寸調べると、下記の太平洋美術会のhttp://www.taiheiyobijutu.or.jp/ryakusi/p_ryakusi.htmに「明治22年小山正太郎、 浅井忠等によって創立された「明治美術会」は同35年 「太平洋画会」と改称し、当時の洋画会の新人満谷国四郎、吉田博、中川八郎、石川寅治、石井柏亭、大下籐次郎、 丸山晩霞等により、 同年3月上野公園第5号館において第1回展を開催しました。 こののち日本近代 美術史の曙を拓いた人々です。明治37年には谷中清水町に洋画研究所を開設し、 翌年同研究所を真島町に移して後進の育成に努め、更に昭和4年には研究所を太平洋美術学校と改め (初代校長・中村不折)官立の美術学校と対抗して、当時、在野における唯一の存在として幾多の英才鬼才をわが国洋画壇に送りました。 」とある。中村不折とは、書の収集家であることを書道博物館で知り、作品も近美に常設展示されているのですが、そのような画家とは、はじめて知りました。
そして、「「池袋モンパルナス」と呼ばれた界隈で仲間たちと切磋琢磨しながら、自らの画風を模索していきます。」とある。「池袋モンパルナス」とは?仲間とは?よく判らない。現在、板橋美術館で館蔵品展「池袋モンパルナスの作家たち」の展覧会が開催されているようだが、「今から80年ほど前、池袋、板橋、練馬付近にはアトリエ付きのアパートが立ちはじめ、若い芸術家たちが集まりました。住人の一人、小熊秀雄はこの界隈の詩を詠んで「池袋モンパルナス」と名づけました。ここでは、麻生三郎、寺田政明、井上長三郎、古沢岩美をはじめとする画家たちが、戦争や貧困の中でキュビスムやシュルレアリスムなど外国の表現を自由に解釈し、独自の芸術を探求していました。政治的、社会的な圧力にも負けず、画家たちは希望に満ちた時代と独自の芸術を明るく捜し求めてい
2007年3月30日から5月27日
東京国立近代美術館
靉光(本名:石村日郎、1907-1946)(AI-MITSU)の生誕100年を記念する展覧会。
いつも常設展に展示されている《眼のある風景》1938年を見て、強烈な印象を受けながら何を描いているのだろうと、不気味に思っていた。
概要で、「1924(大正13)年に上京し、中村不折らが指導する太平洋画会研究所に通うようになる」とあった。一寸調べると、下記の太平洋美術会のhttp://www.taiheiyobijutu.or.jp/ryakusi/p_ryakusi.htmに「明治22年小山正太郎、 浅井忠等によって創立された「明治美術会」は同35年 「太平洋画会」と改称し、当時の洋画会の新人満谷国四郎、吉田博、中川八郎、石川寅治、石井柏亭、大下籐次郎、 丸山晩霞等により、 同年3月上野公園第5号館において第1回展を開催しました。 こののち日本近代 美術史の曙を拓いた人々です。明治37年には谷中清水町に洋画研究所を開設し、 翌年同研究所を真島町に移して後進の育成に努め、更に昭和4年には研究所を太平洋美術学校と改め (初代校長・中村不折)官立の美術学校と対抗して、当時、在野における唯一の存在として幾多の英才鬼才をわが国洋画壇に送りました。 」とある。中村不折とは、書の収集家であることを書道博物館で知り、作品も近美に常設展示されているのですが、そのような画家とは、はじめて知りました。
そして、「「池袋モンパルナス」と呼ばれた界隈で仲間たちと切磋琢磨しながら、自らの画風を模索していきます。」とある。「池袋モンパルナス」とは?仲間とは?よく判らない。現在、板橋美術館で館蔵品展「池袋モンパルナスの作家たち」の展覧会が開催されているようだが、「今から80年ほど前、池袋、板橋、練馬付近にはアトリエ付きのアパートが立ちはじめ、若い芸術家たちが集まりました。住人の一人、小熊秀雄はこの界隈の詩を詠んで「池袋モンパルナス」と名づけました。ここでは、麻生三郎、寺田政明、井上長三郎、古沢岩美をはじめとする画家たちが、戦争や貧困の中でキュビスムやシュルレアリスムなど外国の表現を自由に解釈し、独自の芸術を探求していました。政治的、社会的な圧力にも負けず、画家たちは希望に満ちた時代と独自の芸術を明るく捜し求めてい
_ つまずく石も縁の端くれ - 2007年05月16日 05時05分15秒
靉光(AI-MITSU)の絵はここで、何回も見てきているのだが、昔から「眼のある風景」が何を描いているのか、さっぱり分からなかった。シュルレアリスムの画家だから、さもありなんと思っていたのだが、昨年放映された「美の巨人たち」を見てから、もうライオン以外の何もの...





