Asagi's Art News
次のステージに ~ 東京アートミーティング トランスフォーメーション ― 2011年01月04日 23時17分43秒
この展覧会では、『変身-変容』する形を通して、新たな可能性を考えることを狙いとしているようです。変身といえば、やはり特撮ヒーローが思い浮かびます。不動の人気を持つ仮面ライダーや海を渡っていったトランスフォーマーなど、各世代に想い入れがあると思います。
変わるということは、人が生きていくことで最も大切なことのひとつだと思います。書店をのぞけば、いかに変化して豊かな生活を手に入れるかのハウツー本が山のように積んであることからも判ります。
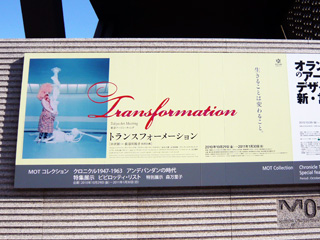
だから、変わるということは何も特別なことではないように思うことも出来るのではないでしょうか。しかし、予想の範囲の変化ではなく、まったく想像できない変化を形にすることは、意外に難しいテーマなのかもしれません。
それぞれの作品は考えられ良くできているのですが、例えば、人と人以外の何かの融合であれば、オブジェにしても映像にしても残念ですが、先にも言った特撮ヒーローの発想とあまり変わらないように思えます。
感じ方の違いかもしれませんが、表面的なあるいは物質的な変化よりも、精神的なあるいは感覚的な変化を表現するのが良いように思います。いかにも切ったり貼ったりしたことが判るの作品では、何か物足りない感じがするのです。
その意味では、及川潤耶(1983-)の『transformation 2010』という作品は、視覚でなく聴覚から体験するインスタレーションでとても良かったと思います。照明のない部屋の中にスピーカーをいくつか設置して、それぞれのスピーカーから自然の音(物音や気配)や動物の鳴き声などをランダムに発生させます。
いままでに経験してきたことの差はあるかもしれませんが、音だけで見えないことによる想像の展開に圧倒されます。自分自身の姿も確認できないことから、体が空間と融合することで、あるはずのない森や空や大地を感じることが出来ます。生命体として次のステージに移行したような感じなのです。
ほんの少し時間だったのですが、何か変化したような体験ができました。視覚以外の表現方法は、賛否があるかもしれません。しかし、新しい発見がまだまだたくさんあるように思います。インスタレーションによる表現の幅を広げるためにも、このような作品をどんどん発表してほしいと思います。
※東京都現代美術館(2010年10月29日~2011年1月30日)
変わるということは、人が生きていくことで最も大切なことのひとつだと思います。書店をのぞけば、いかに変化して豊かな生活を手に入れるかのハウツー本が山のように積んであることからも判ります。
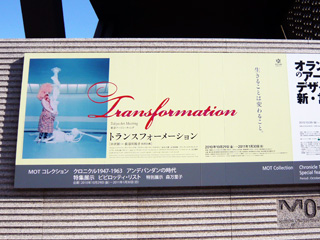
だから、変わるということは何も特別なことではないように思うことも出来るのではないでしょうか。しかし、予想の範囲の変化ではなく、まったく想像できない変化を形にすることは、意外に難しいテーマなのかもしれません。
それぞれの作品は考えられ良くできているのですが、例えば、人と人以外の何かの融合であれば、オブジェにしても映像にしても残念ですが、先にも言った特撮ヒーローの発想とあまり変わらないように思えます。
感じ方の違いかもしれませんが、表面的なあるいは物質的な変化よりも、精神的なあるいは感覚的な変化を表現するのが良いように思います。いかにも切ったり貼ったりしたことが判るの作品では、何か物足りない感じがするのです。
その意味では、及川潤耶(1983-)の『transformation 2010』という作品は、視覚でなく聴覚から体験するインスタレーションでとても良かったと思います。照明のない部屋の中にスピーカーをいくつか設置して、それぞれのスピーカーから自然の音(物音や気配)や動物の鳴き声などをランダムに発生させます。
いままでに経験してきたことの差はあるかもしれませんが、音だけで見えないことによる想像の展開に圧倒されます。自分自身の姿も確認できないことから、体が空間と融合することで、あるはずのない森や空や大地を感じることが出来ます。生命体として次のステージに移行したような感じなのです。
ほんの少し時間だったのですが、何か変化したような体験ができました。視覚以外の表現方法は、賛否があるかもしれません。しかし、新しい発見がまだまだたくさんあるように思います。インスタレーションによる表現の幅を広げるためにも、このような作品をどんどん発表してほしいと思います。
※東京都現代美術館(2010年10月29日~2011年1月30日)
美しいおっぱい ~ いのちの乳房 ― 2011年01月10日 10時02分25秒
笑顔に目が奪われるヌード写真集が、本屋さん(紀伊国屋書店)に並べられていました。『いのちの乳房』という写真集です。この写真はもしかしてと思い確認すると、やっぱりアラーキーこと荒木経惟(1940-)の撮った写真でした。
なぜ、彼女たちの笑顔は輝いているのか? その秘密は、彼女たちのおっぱいにありました。日本女性の乳がんは、約30人にひとりの割合で見つかります(男性にも見つかりますが、女性に比べると数は少ない)。もちろん、検査も進歩してきていますが、命を失うケースも多いとても怖い病気です。
命が助かったとしても、肉体的、精神的に苦痛をともなうことがあります。特に乳房の切除に至った場合の精神的な痛みは、はかりしれない苦痛となります。第三者は、命に比べればと思いがちですが、おっぱいひとつで生きて行くことさえ苦痛になるのです。
この写真集は、そうした多くの女性に向け「乳房再建手術」を提案するとともに、生きることの大切さを示しているように思います。そこには、グラビア写真集に出てくるようなきれいなおっぱいはありません。しかし、その人の誇りと新しい人生を見つけることができるのです。そこにあるのは、美しいおっぱいです。
かつて岡村太郎(1911-1996)は、こんなこと言っていました。きれいな人は、ただきれいだなと思うだけで、気にとめることはない。しかし、きれいではないが、何か惹きつけられる人がいる。そのひとがすばらしい人なら、つきあっているうちにだんだん美しさが輝いてくるような感じがして、やがて本当にきれいであるような気になってくる。そんな人は、美しい。
この本は、そんな人たちがモデルの写真集なのです。そして、モデルである彼女たちが、選んだ写真家がアラーキーだったのも何故か納得がいくように思います。アラーキーは、猥雑なイメージの作品も多く手掛けていますが、最愛の人を亡くすなど死や絶望を経験していて、とても暖かで愛情のある作品も撮っています。
死や絶望を見つめ、新たに生きる希望を見つける。どん底から這い上がってくるのも、また人生なのかもしれません。モデルたちが写真家を呼び寄せ共鳴しています。希望は笑顔であり、誇りは新しい体なのです。
※「いのちの乳房」オフィシャルサイト
なぜ、彼女たちの笑顔は輝いているのか? その秘密は、彼女たちのおっぱいにありました。日本女性の乳がんは、約30人にひとりの割合で見つかります(男性にも見つかりますが、女性に比べると数は少ない)。もちろん、検査も進歩してきていますが、命を失うケースも多いとても怖い病気です。
命が助かったとしても、肉体的、精神的に苦痛をともなうことがあります。特に乳房の切除に至った場合の精神的な痛みは、はかりしれない苦痛となります。第三者は、命に比べればと思いがちですが、おっぱいひとつで生きて行くことさえ苦痛になるのです。
この写真集は、そうした多くの女性に向け「乳房再建手術」を提案するとともに、生きることの大切さを示しているように思います。そこには、グラビア写真集に出てくるようなきれいなおっぱいはありません。しかし、その人の誇りと新しい人生を見つけることができるのです。そこにあるのは、美しいおっぱいです。
かつて岡村太郎(1911-1996)は、こんなこと言っていました。きれいな人は、ただきれいだなと思うだけで、気にとめることはない。しかし、きれいではないが、何か惹きつけられる人がいる。そのひとがすばらしい人なら、つきあっているうちにだんだん美しさが輝いてくるような感じがして、やがて本当にきれいであるような気になってくる。そんな人は、美しい。
この本は、そんな人たちがモデルの写真集なのです。そして、モデルである彼女たちが、選んだ写真家がアラーキーだったのも何故か納得がいくように思います。アラーキーは、猥雑なイメージの作品も多く手掛けていますが、最愛の人を亡くすなど死や絶望を経験していて、とても暖かで愛情のある作品も撮っています。
死や絶望を見つめ、新たに生きる希望を見つける。どん底から這い上がってくるのも、また人生なのかもしれません。モデルたちが写真家を呼び寄せ共鳴しています。希望は笑顔であり、誇りは新しい体なのです。
※「いのちの乳房」オフィシャルサイト
ちょっぴり夕焼け ~ 山下公園 ― 2011年01月16日 23時28分08秒
小さなリズム ~ 櫃田伸也展 ― 2011年01月22日 00時17分20秒
恒例の東郷青児美術館大賞受賞記念の展覧会ですが、今年は抽象画の櫃田信也(ひつだのぶや)(1941-)が選ばれています。櫃田は東京藝術大学で油絵を学び、卒業後は愛知県立芸術大学などで後輩を育成しながら、創作活動を続けてきたそうです。

最近では、あいちトリエンナーレにおいて、後輩で教え子でもある奈良義智(1959-)などとアートイベントを立ち上げるなど活発な活動をしています。『通り過ぎた風景』と題したシリーズなど、どこにでもあるような風景を具象部分を残し、かつ、抽象化するような作品を手掛けています。
大賞受賞作の『不確かな風景』は、その代表的な作品と言えます。控えめな色調が全面を占めているのですが、中心になる形には原色に近いはっきりした色を使い、アクセントを持たせています。リズミカルで心地良い配置に安心感があると思います。
風景画としては、ユトリロ(1883-1955)の作品を意識しているようにも思いますが、リズムというところからは、デュフィ(1877-1953)を加えているような感じがします。あさぎが良いなと思った作品は、他の作品と違い青をメインの色に使った『洪水』という作品です。

櫃田信也「洪水、2003」
少しメルヘンチックな感じもして、とてもきれいな仕上がりになっています。洪水というよりも、水中に沈んだ世界のように思います。中心にある家は廃墟のようで静寂を演出するのですが、部屋や壁の作りが小さなリズムを奏でているような感じがします。とても静かで深い世界に迷い込んだ気分です。
※損保ジャパン東郷青児美術館

最近では、あいちトリエンナーレにおいて、後輩で教え子でもある奈良義智(1959-)などとアートイベントを立ち上げるなど活発な活動をしています。『通り過ぎた風景』と題したシリーズなど、どこにでもあるような風景を具象部分を残し、かつ、抽象化するような作品を手掛けています。
大賞受賞作の『不確かな風景』は、その代表的な作品と言えます。控えめな色調が全面を占めているのですが、中心になる形には原色に近いはっきりした色を使い、アクセントを持たせています。リズミカルで心地良い配置に安心感があると思います。
風景画としては、ユトリロ(1883-1955)の作品を意識しているようにも思いますが、リズムというところからは、デュフィ(1877-1953)を加えているような感じがします。あさぎが良いなと思った作品は、他の作品と違い青をメインの色に使った『洪水』という作品です。

櫃田信也「洪水、2003」
少しメルヘンチックな感じもして、とてもきれいな仕上がりになっています。洪水というよりも、水中に沈んだ世界のように思います。中心にある家は廃墟のようで静寂を演出するのですが、部屋や壁の作りが小さなリズムを奏でているような感じがします。とても静かで深い世界に迷い込んだ気分です。
※損保ジャパン東郷青児美術館
素直な気持ち ~ 特別支援学級・新宿養護学校連合作品展 ― 2011年01月24日 23時54分13秒
たまたま通りがかりだったのですが、元気のある良い作品たちに出会いました。いつもは休憩所になってるスペースなのですが、絵画、版画をはじめ小さな造形作品や陶芸など、さまざまな作品がひしめき合いながら紹介されていました。

この展覧会は、新宿区にある特別支援学級や養護学校の生徒たちが、1年を通して作ってきた作品の発表の場であると同時に、彼らが社会の一員として日々努力していることを伝える意味もあるのだと思います。
アートの世界では、プロもアマも同じ土俵の上に立ち作成をします。そして、その結果は大人であろうと、子どもであろうと、身体にハンディがあろうと、何も関係なく等しく評価されるのです。もちろん、努力がすべて報われるわけではありませんが、自由なフィールドがあることはすべての人に共通なのです。

ひとつでも多くの作品を見せたい気持ちから、展示方法には多少無理があります。しかし、雑然とした中の作品を注意深く見てみると、とても個性的であり、楽しく制作している姿が想像できます。いきいきとしたパワーがあるのです。
なんとなく遠い昔に同じ方法で作品を作ったことを思い出しました。あのときは、あんな苦労をしたとか、あそこが楽しいとか、子どもたちの作品から忘れていたものをプレゼントされたようです。



彼ら自身は、意識していないのかもしれませんが、絵画ならば絶妙な構図やドキッとするような配色のものがあったりして驚きます。素直な気持ちで作品と向き合っているのだと思います。そして、繰り返しますが、どの作品からも元気をもらうことができます。
大人になると技術が身についたり、他の人の作品を意識するようになって、だんだんつまらないものになっていくことが通例です…彼らにしても同じなのかもしれません。そこに、一抹の寂しさがあるのですが、展覧会は毎年続いているようなので、これからも楽しみな作品を見ることができそうでなによりです。
※損保ジャパンビル(2010年1月18日~2010年1月30日)

この展覧会は、新宿区にある特別支援学級や養護学校の生徒たちが、1年を通して作ってきた作品の発表の場であると同時に、彼らが社会の一員として日々努力していることを伝える意味もあるのだと思います。
アートの世界では、プロもアマも同じ土俵の上に立ち作成をします。そして、その結果は大人であろうと、子どもであろうと、身体にハンディがあろうと、何も関係なく等しく評価されるのです。もちろん、努力がすべて報われるわけではありませんが、自由なフィールドがあることはすべての人に共通なのです。

ひとつでも多くの作品を見せたい気持ちから、展示方法には多少無理があります。しかし、雑然とした中の作品を注意深く見てみると、とても個性的であり、楽しく制作している姿が想像できます。いきいきとしたパワーがあるのです。
なんとなく遠い昔に同じ方法で作品を作ったことを思い出しました。あのときは、あんな苦労をしたとか、あそこが楽しいとか、子どもたちの作品から忘れていたものをプレゼントされたようです。



彼ら自身は、意識していないのかもしれませんが、絵画ならば絶妙な構図やドキッとするような配色のものがあったりして驚きます。素直な気持ちで作品と向き合っているのだと思います。そして、繰り返しますが、どの作品からも元気をもらうことができます。
大人になると技術が身についたり、他の人の作品を意識するようになって、だんだんつまらないものになっていくことが通例です…彼らにしても同じなのかもしれません。そこに、一抹の寂しさがあるのですが、展覧会は毎年続いているようなので、これからも楽しみな作品を見ることができそうでなによりです。
※損保ジャパンビル(2010年1月18日~2010年1月30日)






