Asagi's Art News
デリケートな展覧会 ~ DOMANI・明日展 ― 2012年02月01日 23時55分29秒
今年もDOMANI・明日展が開催されました。文化庁が主催する若手アーティストの海外派遣の成果報告となる展覧会ですが、さまざまな分野での派遣をしています。DOMANI・明日展としては、1998年から今年で14回目となります。
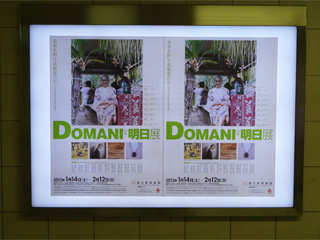
8人のアーティストがエントリーされています。阿部守(1954-)は鉄の彫刻、山口牧子(1962-)は抽象絵画、横澤典(1971-)は写真、元田久治(1973-)は想像風景の版画、津田睦美(1962-)は写真、児嶋サコ(1976-)はアニマル系絵画、綿引展子(1958-)は絵画のような造形、塩谷亮(1975-)は写実絵画と言った感じです。
それぞれのアーティストが独立した個性を持っていることから、展示スペースが変わるたびに違った印象を受けます。お互いの作品が相互作用をしない変わりに印象が薄くなってしまったり、その良さが伝わないことがあるようです。
新美術館の大きなスペースをゆったり使っているので、時間をかけて鑑賞するには良いのですが、少し足早に見ていくと展覧会の欠点が見えてしまうかもしれません。鑑賞側もちょっと気をつけないとならないデリケートな展覧会なのだと思います。
そのような中から良いなと思った作品は、元田久治の版画の世界でした。彼の作品は見慣れた東京の風景だったりするのですが、良く見ると 描かれている建物は朽ちていたり、壊れていたりします。近未来のSFの世界感を受けます。

元田久治「Indication-Tokyo Tower 5、2007」
インタビューの記事を見ると坂本龍一や村上春樹が好きとあったので、何となくですがイメージする世界観が想像できるように思いました。静かで緻密な版画は、そのイメージにぴったりのようです。
※国立新美術館(2012年1月14日~2012年2月12日)
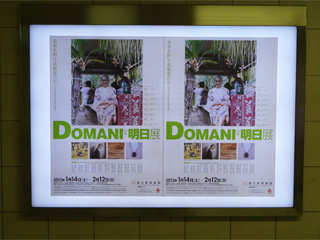
8人のアーティストがエントリーされています。阿部守(1954-)は鉄の彫刻、山口牧子(1962-)は抽象絵画、横澤典(1971-)は写真、元田久治(1973-)は想像風景の版画、津田睦美(1962-)は写真、児嶋サコ(1976-)はアニマル系絵画、綿引展子(1958-)は絵画のような造形、塩谷亮(1975-)は写実絵画と言った感じです。
それぞれのアーティストが独立した個性を持っていることから、展示スペースが変わるたびに違った印象を受けます。お互いの作品が相互作用をしない変わりに印象が薄くなってしまったり、その良さが伝わないことがあるようです。
新美術館の大きなスペースをゆったり使っているので、時間をかけて鑑賞するには良いのですが、少し足早に見ていくと展覧会の欠点が見えてしまうかもしれません。鑑賞側もちょっと気をつけないとならないデリケートな展覧会なのだと思います。
そのような中から良いなと思った作品は、元田久治の版画の世界でした。彼の作品は見慣れた東京の風景だったりするのですが、良く見ると 描かれている建物は朽ちていたり、壊れていたりします。近未来のSFの世界感を受けます。

元田久治「Indication-Tokyo Tower 5、2007」
インタビューの記事を見ると坂本龍一や村上春樹が好きとあったので、何となくですがイメージする世界観が想像できるように思いました。静かで緻密な版画は、そのイメージにぴったりのようです。
※国立新美術館(2012年1月14日~2012年2月12日)
絵画が築かれた光景 ~ 野田裕示 絵画のかたち/絵画の姿 ― 2012年02月04日 00時12分32秒
今年、国立新美術館は、開館5周年を迎えました。5周年の企画もいろいろとあったようですが、当日は静かに特別の無料開放と特設会場(1階フロアの入口に近いところ)の講演など行ったようです。

野田裕示展も無料開放の企画展で、せっかくなので鑑賞をさせてもらってきました。実はこの企画展も3.11の地震の影響で、開催が延期になった展覧会です。遅くなったとは言えど、ちゃんと展覧会が開催されることは単に嬉しいことだと思います。
さて、主役の野田裕示(1952-)という画家についてですが、実は良く知りませんでした。しかし、多摩美術大学の油絵科を卒業後、実験的でダイナミックな作品に注目が集め、日本における現代美術の先駆的な存在であるとプロフィールにありました。
一貫して支持体(絵画の塗膜を支える面を構成する物質)と絵画との関係を追求してると言っています。なかなか理解しづらいことですが、例えば、キャンバスの変わりに石を用いて、アクリル絵の具でペイントをしたり、立体と平面を組み合わせた試みなどの作品があります。
抽象という概念とも少し違う…支持体と絵画の組み合わせから展開して、描くというよりは建築のように築きあげるような感覚なのかもしれません。そして、絵画が築かれた光景は、単純な色と形から構成されることで強烈な印象をあたえてくれるのです。
※国立新美術館(2012年1月18日~2012年4月2日)

野田裕示展も無料開放の企画展で、せっかくなので鑑賞をさせてもらってきました。実はこの企画展も3.11の地震の影響で、開催が延期になった展覧会です。遅くなったとは言えど、ちゃんと展覧会が開催されることは単に嬉しいことだと思います。
さて、主役の野田裕示(1952-)という画家についてですが、実は良く知りませんでした。しかし、多摩美術大学の油絵科を卒業後、実験的でダイナミックな作品に注目が集め、日本における現代美術の先駆的な存在であるとプロフィールにありました。
一貫して支持体(絵画の塗膜を支える面を構成する物質)と絵画との関係を追求してると言っています。なかなか理解しづらいことですが、例えば、キャンバスの変わりに石を用いて、アクリル絵の具でペイントをしたり、立体と平面を組み合わせた試みなどの作品があります。
抽象という概念とも少し違う…支持体と絵画の組み合わせから展開して、描くというよりは建築のように築きあげるような感覚なのかもしれません。そして、絵画が築かれた光景は、単純な色と形から構成されることで強烈な印象をあたえてくれるのです。
※国立新美術館(2012年1月18日~2012年4月2日)
秘めた思いや感情 ~ 松井冬子展 ― 2012年02月10日 23時44分10秒
ここ最近、かなりの頻度でマスメディアに登場している松井冬子(1974-)。彼女の言葉で自身の世界観を語ることは、たいへん興味深いことだと思います。作品のみならず彼女自身にも人気があり、特に若い人たちは彼女の影響を大いに受けて何かを感じているようです。

そのため、展覧会の会場には学生やそれに近い年齢層の若い人たちがたくさんやって来ていました。もちろん、時間帯による偏りがあると思うのですが、特に目立つのは普段あまり見かけない若い男性の姿…何かちょっと違った感じがありました。
たぶんですが、彼女が知的な美人ということも要因であると思います。だから、彼女のファンの男性がたくさん集まった感じなのかもしれません。作品はアーティストの分身であるとも言いますから、作品と触れ合うことでいろいろ感じるところがあるのでしょう。
さて、展覧会ですが、初期の作品から最近の作品まで、幅広く展示されていました。横浜美術館が所蔵する「世界中の子と友達になれる」は、常設の展示ではガラスケースの中にあるのですが、この展覧会ではガラスなしで見ることが出来ます。
細かい描き込みをじっくり見ることが出るのは、なかなかない機会で大変嬉しいことです。また、「世界中の子と友達になれる」と同じエリアに藝大卒業時に制作された自画像がありました。この自画像の作成にあっては、彼女がいろいろ語っていて、それを思い出しながら見るのもちょっと楽しかったりします。
はじめて見る作品もたくさんあって、その中でも印象風景の大作「この疾患を治癒させるために破壊する」は、とても良い作品だと思いました。日本画ならではの広がりと静寂さの中に、見方によっては美しいと言うよりも官能的な部分がひそんでいるように思います。

松井冬子「この疾患を治癒させるために破壊する、2004」
タイトルから感じる印象はシュルレアリスムのような意味深い感じがするのですが、実際にはもっとストレートに伝わって来る感じだと思います。彼女の心の中にある秘めた思いや感情…そのようなものを感じます。かなりハードで直接的な表現をする作品もありますが、このように間接的な表現もとても魅力を感じることが出来ます。
※横浜美術館(2011年12月17日~2012年3月18日)

そのため、展覧会の会場には学生やそれに近い年齢層の若い人たちがたくさんやって来ていました。もちろん、時間帯による偏りがあると思うのですが、特に目立つのは普段あまり見かけない若い男性の姿…何かちょっと違った感じがありました。
たぶんですが、彼女が知的な美人ということも要因であると思います。だから、彼女のファンの男性がたくさん集まった感じなのかもしれません。作品はアーティストの分身であるとも言いますから、作品と触れ合うことでいろいろ感じるところがあるのでしょう。
さて、展覧会ですが、初期の作品から最近の作品まで、幅広く展示されていました。横浜美術館が所蔵する「世界中の子と友達になれる」は、常設の展示ではガラスケースの中にあるのですが、この展覧会ではガラスなしで見ることが出来ます。
細かい描き込みをじっくり見ることが出るのは、なかなかない機会で大変嬉しいことです。また、「世界中の子と友達になれる」と同じエリアに藝大卒業時に制作された自画像がありました。この自画像の作成にあっては、彼女がいろいろ語っていて、それを思い出しながら見るのもちょっと楽しかったりします。
はじめて見る作品もたくさんあって、その中でも印象風景の大作「この疾患を治癒させるために破壊する」は、とても良い作品だと思いました。日本画ならではの広がりと静寂さの中に、見方によっては美しいと言うよりも官能的な部分がひそんでいるように思います。

松井冬子「この疾患を治癒させるために破壊する、2004」
タイトルから感じる印象はシュルレアリスムのような意味深い感じがするのですが、実際にはもっとストレートに伝わって来る感じだと思います。彼女の心の中にある秘めた思いや感情…そのようなものを感じます。かなりハードで直接的な表現をする作品もありますが、このように間接的な表現もとても魅力を感じることが出来ます。
※横浜美術館(2011年12月17日~2012年3月18日)
グラン・ブーケ ~ ルドンとその周辺-夢見る世紀末 ― 2012年02月15日 22時44分57秒
三菱一号館美術館が作品の収集に力を入れていることを示すように、所蔵が決まったオディロン・ルドン(1840-1916)の『グラン・ブーケ』を中心とした展覧会でした。注目の作品の大きさは、162.9cm×248.3cmと、稀に見る大きなパステル画です。

展覧会はルドンの回顧展となっているのですが、やっぱり最初から気になるのは『グラン・ブーケ』です。展示も初期の作品、「黒のルドン」と言われた版画、そして、良く知られている色彩豊かな作品と一通り揃えています。また、ルドンとその時代の画家の作品もあって回顧展としては濃い内容です。
しかし、美術館の力の入れようが『グラン・ブーケ』一色であるため、もう気になってしかたがないと言う状況を作り出しています。大人しく歴史を辿りながらの鑑賞も良いのですが、迷わず『グラン・ブーケ』に直行した方が良かったかもしれません。

オディロン・ルドン「グラン・ブーケ、1901」
美術館の構造上、作品の配置には苦労していると思っています。また、注目される作品をどこに配置するのかも悩むところだと思っています。今回は、中盤の折り返しを少し過ぎたところ…中間点と言っても良いところに『グラン・ブーケ』を持ってきていました。なので、なかなか出て来ないという感じがしました。
そして、いよいよ対面となるのですが、パステル画であるため照明は最小限です。しかし、それが作品の大きさをさらに強調する効果があるようで、薄暗い中に浮かびあがる花束には、かなり圧倒される感じがします。色も鮮やかで良い演出をしていると思いました。
『グラン・ブーケ』は三菱一号館美術館の所蔵品ですから、機会があるたびに展示されることもあると思います。なので、会場に行くまでは、今回見逃してしまっても良いかななどと思っていたのですが、やっぱり見に行って良かったと最後は納得して帰って来ました。
※三菱一号館美術館(2012年1月17日~2012年3月4日)

展覧会はルドンの回顧展となっているのですが、やっぱり最初から気になるのは『グラン・ブーケ』です。展示も初期の作品、「黒のルドン」と言われた版画、そして、良く知られている色彩豊かな作品と一通り揃えています。また、ルドンとその時代の画家の作品もあって回顧展としては濃い内容です。
しかし、美術館の力の入れようが『グラン・ブーケ』一色であるため、もう気になってしかたがないと言う状況を作り出しています。大人しく歴史を辿りながらの鑑賞も良いのですが、迷わず『グラン・ブーケ』に直行した方が良かったかもしれません。

オディロン・ルドン「グラン・ブーケ、1901」
美術館の構造上、作品の配置には苦労していると思っています。また、注目される作品をどこに配置するのかも悩むところだと思っています。今回は、中盤の折り返しを少し過ぎたところ…中間点と言っても良いところに『グラン・ブーケ』を持ってきていました。なので、なかなか出て来ないという感じがしました。
そして、いよいよ対面となるのですが、パステル画であるため照明は最小限です。しかし、それが作品の大きさをさらに強調する効果があるようで、薄暗い中に浮かびあがる花束には、かなり圧倒される感じがします。色も鮮やかで良い演出をしていると思いました。
『グラン・ブーケ』は三菱一号館美術館の所蔵品ですから、機会があるたびに展示されることもあると思います。なので、会場に行くまでは、今回見逃してしまっても良いかななどと思っていたのですが、やっぱり見に行って良かったと最後は納得して帰って来ました。
※三菱一号館美術館(2012年1月17日~2012年3月4日)
活動 ~ 日本赤十字社所蔵アート展 ― 2012年02月25日 22時45分25秒
日本赤十字社が所蔵する作品を公開する展覧会になります。西南戦争から130年の歴史を持つ日本赤十字社ですが、その活動に賛同する画家も多くいます。そのため、活動に協力するために寄贈された作品も数多く存在しています。

会場となっている損保ジャパン東郷青児美術館のコレクションでもある東郷青児(1897-1978)の作品をはじめ小磯良平(1903-1988)、東山魁夷(1908-1999)、梅原龍三郎(1888-1986)など巨匠が揃って寄贈をしています。
作品のテーマも赤十字の理想とする人道的任務を直接あるいは間接的に表現している作品が多いように思います。なので、描き下ろしの作品もかなりあります。しかし、梅原龍三郎のように描き下ろしに拘っていたが婦人の不幸でそれがかなわず、その事情を知った人から彼の作品を寄贈したなどのエピソードもあるようです。
折しも東日本大震災が起こり、日本赤十字社も多くの寄付を集め復興のために活動をしています。この展覧会でも入場料を義援金として寄付をする旨が説明されていました。小さいことですが、展覧会を通して復興の一部に貢献できるのは、とても嬉しいことだと思います。
※損保ジャパン東郷青児美術館(2012年1月7日~2012年2月19日)

会場となっている損保ジャパン東郷青児美術館のコレクションでもある東郷青児(1897-1978)の作品をはじめ小磯良平(1903-1988)、東山魁夷(1908-1999)、梅原龍三郎(1888-1986)など巨匠が揃って寄贈をしています。
作品のテーマも赤十字の理想とする人道的任務を直接あるいは間接的に表現している作品が多いように思います。なので、描き下ろしの作品もかなりあります。しかし、梅原龍三郎のように描き下ろしに拘っていたが婦人の不幸でそれがかなわず、その事情を知った人から彼の作品を寄贈したなどのエピソードもあるようです。
折しも東日本大震災が起こり、日本赤十字社も多くの寄付を集め復興のために活動をしています。この展覧会でも入場料を義援金として寄付をする旨が説明されていました。小さいことですが、展覧会を通して復興の一部に貢献できるのは、とても嬉しいことだと思います。
※損保ジャパン東郷青児美術館(2012年1月7日~2012年2月19日)





