Asagi's Art News
桜散って ~ 頭山 ― 2006年05月01日 00時19分22秒
東京では桜は終わってしまいましたが、東北ではまだまだ見ごろだそうです。桜ということではないのですが、少し前の作品ですが、日本のアニメーションも頑張ってると思った作品のDVDを手に入れてみました。
『頭山』、アカデミー賞にもノミネートされたことのある短編アニメーションです。ある男の頭に桜の木が生えてたいへんなことが起きるこの作品は、落語『頭山』を原作にしています。
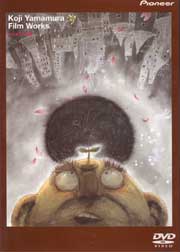
山村浩二「頭山、2002」
そうとはいっても落語の方は、なにも知りません。そこまで追求するつもりもありません。物語は、けちな男がさくらんぼうを拾って食べるのですが、もったいないと言うことでさくらんぼうの種まで食べてしまいます。
すると不思議なことに男の頭に桜の芽が生えてきます。最初のうちは気にして芽を摘んでいたのですが、やがて面倒くさくなったのかそのままにしてしまいます。するると、桜は成長して立派な木に成長し見後な花を咲かせるのでした。
やがて、桜は評判となり多くの人がお花見にやってくることになりました。 頭の上で飲めや歌えの大騒ぎ、男のいらいらが頂点に達した時、男は桜を・・。このような感じで、落語なので決まっておちがあるのですが、あさぎにはいまひとつ良く判りません。
ただ、短編で意味深い作品であることが感じられ、哀れな男に哀愁が漂っています。アニメーションが作る現実離れした世界は、とても哲学的な要素を持っているようです。男の暮らす世界と桜のある世界がパラレルワールドになって無限を示しているかのようです。
アートアニメーションという聞きなれない言葉があるらしいのですが、この『頭山』を見ているとそんな感じがしてきます。テレビで流れているアニメを嫌っているわけではないのですが、どちらが素敵に見えるかとなるとあさぎはこちらの方に傾いてしまいます。
『頭山』、アカデミー賞にもノミネートされたことのある短編アニメーションです。ある男の頭に桜の木が生えてたいへんなことが起きるこの作品は、落語『頭山』を原作にしています。
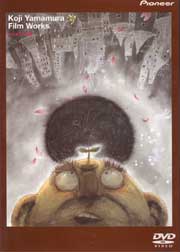
山村浩二「頭山、2002」
そうとはいっても落語の方は、なにも知りません。そこまで追求するつもりもありません。物語は、けちな男がさくらんぼうを拾って食べるのですが、もったいないと言うことでさくらんぼうの種まで食べてしまいます。
すると不思議なことに男の頭に桜の芽が生えてきます。最初のうちは気にして芽を摘んでいたのですが、やがて面倒くさくなったのかそのままにしてしまいます。するると、桜は成長して立派な木に成長し見後な花を咲かせるのでした。
やがて、桜は評判となり多くの人がお花見にやってくることになりました。 頭の上で飲めや歌えの大騒ぎ、男のいらいらが頂点に達した時、男は桜を・・。このような感じで、落語なので決まっておちがあるのですが、あさぎにはいまひとつ良く判りません。
ただ、短編で意味深い作品であることが感じられ、哀れな男に哀愁が漂っています。アニメーションが作る現実離れした世界は、とても哲学的な要素を持っているようです。男の暮らす世界と桜のある世界がパラレルワールドになって無限を示しているかのようです。
アートアニメーションという聞きなれない言葉があるらしいのですが、この『頭山』を見ているとそんな感じがしてきます。テレビで流れているアニメを嫌っているわけではないのですが、どちらが素敵に見えるかとなるとあさぎはこちらの方に傾いてしまいます。
自然と人間 ~ 木を植えた男 ― 2006年05月02日 16時46分12秒
この『木を植えた男』が、誕生してから20年もの歳月が過ぎようとしています。あさぎが、アニメでなくアニメーションに興味を持ったはじめての作品です。フレデリック・バックの作品は、とてもメッセージ性が高く、自然と人間の関係をバブル時代の前から訴え続けています。
たぶん、この作品を見たことのない人は、最近の環境問題とかに結びつけて考えると思うのですが、なぜかあさぎとしては、この一連のエコブームとは一緒に考えて欲しくないような気がしています。
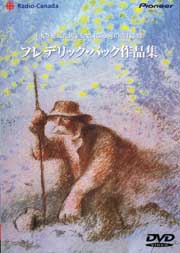
フレデリック・バック「木を植える男、1987」
はじめてこの作品に出会ったとき、パステルの絵が動き出すことに感動して、その中にあるメッセージにショックを受けたことを思い出しました。遠い記憶のような気がします。まだ、若かったのかな・・
はじまりの暗い寂しい風景が、やがて木々たちの成長を見るように色づきカラフルになってきます。パルテルの持つ暖かさが画面からも伝わってきて、いま見ても木々の緑は、まるで生きているように思えます。
一人の男が行ったことを「人のなす業が神の行ないにも匹敵する・・」と作品の中でも言っいるように人間としての奇跡なのです。そして、その奇跡とは逆の行為として出てくるのが戦争です。本編にはさりげなく、第1次大戦と第2次大戦が出てきます。
木を植え森に返すことと破壊を繰り返す戦争は、相反することであるけれどどちらも人間が行うことです。この矛盾に対して疑問を投げかけ、人間が何をするべきなのかを訴えているように思えます。
あさぎが、エコブームに対して持っている疑問点は、たぶんこの矛盾があるからでしょう。環境問題を考えることは大切なことです。しかし、人間の都合の良い環境を守るように見えてしまうエコブームは、ちゃんと人間のもつ矛盾を考えて進めなければすぐに終ってしまうように感じています。
たぶん、この作品を見たことのない人は、最近の環境問題とかに結びつけて考えると思うのですが、なぜかあさぎとしては、この一連のエコブームとは一緒に考えて欲しくないような気がしています。
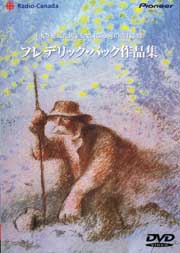
フレデリック・バック「木を植える男、1987」
はじめてこの作品に出会ったとき、パステルの絵が動き出すことに感動して、その中にあるメッセージにショックを受けたことを思い出しました。遠い記憶のような気がします。まだ、若かったのかな・・
はじまりの暗い寂しい風景が、やがて木々たちの成長を見るように色づきカラフルになってきます。パルテルの持つ暖かさが画面からも伝わってきて、いま見ても木々の緑は、まるで生きているように思えます。
一人の男が行ったことを「人のなす業が神の行ないにも匹敵する・・」と作品の中でも言っいるように人間としての奇跡なのです。そして、その奇跡とは逆の行為として出てくるのが戦争です。本編にはさりげなく、第1次大戦と第2次大戦が出てきます。
木を植え森に返すことと破壊を繰り返す戦争は、相反することであるけれどどちらも人間が行うことです。この矛盾に対して疑問を投げかけ、人間が何をするべきなのかを訴えているように思えます。
あさぎが、エコブームに対して持っている疑問点は、たぶんこの矛盾があるからでしょう。環境問題を考えることは大切なことです。しかし、人間の都合の良い環境を守るように見えてしまうエコブームは、ちゃんと人間のもつ矛盾を考えて進めなければすぐに終ってしまうように感じています。
未来的展覧会 ~ ダ・ヴィンチ・コード展 ― 2006年05月03日 00時04分18秒
世界的なベストセラーであり、もうすぐ映画も公開される『ダ・ヴィンチ・コード』の予備知識を深めるための展覧会らしいのですが、少し即席でやってしまったとう感じが抜けません。ゴールデンウェークに間に合わせかったのでしょう。
ミステリーは苦手で読みませんが、この『ダ・ヴィンチ・コード』はお正月休みに読んでいました。しかも、挿絵の付いている愛蔵版を買って・・。ミステリーは、内容が判ってしまうとつまらないので、ここでは書きませんが、世間が騒いでいるほどビックリすることはなかったと言うのが感想です。
何を深く追求するのかが気になって、話題の六本木ヒルズまで出かけたのですが、普通の絵画を見慣れているあさぎにとっては、ちょっとと思うところもたくさんありました。そうそう、入館料が高いのは場所代と割り切ることにした方が良さそうです。
展示内容は、ミステリーのキーポイントを動画とオブジェで構成しています。動画には、液晶テレビとプロジェクションが使われていて、なんとなく未来的な感じがしました。将来、絵画のオリジナルがなくなってしまったときとか、遠隔地で鑑賞するする場合にこんな形になるのかなと思ったりしました。
しかしというか、当然というか、オリジナルとはぜんぜん違います。まず、作品自体の存在感がいまひとつであること(たぶん、コントラストと質感の問題と思います)。鑑賞モードと解説モードがあっておもしろいのですが、大きなコンピュータ画面を見ているようでさみしい感じがします。
オリジナルに拘らないでインスタレーションのような展示をした方が良かったのではと思ってしまいます。作品は、アートではなく、インフォメーションなのだと思いました。デジタル社会の縮図のような気がします。
あまり良いとことがなかったのですが、ひとつだけ良かった作品がありました。それは、実物大の『最後の晩餐』のデジタル画像です。どう頑張ってもサンタ・マリア・デレ・グラーツィエ聖堂から持ってくることは不可能ですし、本物ではコントラストの問題もあって鮮明には見えないと思います。
大きさだけは、同じですからその迫力は伝わってきます。デジタルと言ううだけに綺麗です。ただ、文句があるとすれば、余計な解説や音楽は要らないので静かにゆっくり見せて欲しかったです。妙な演出で全体を台無しにしているように思いました。

レオナルド・ダ・ヴィンチ「最後の晩餐、1498」
※森アーツセンターギャラリー
※ダ・ヴィンチ・コード展
ミステリーは苦手で読みませんが、この『ダ・ヴィンチ・コード』はお正月休みに読んでいました。しかも、挿絵の付いている愛蔵版を買って・・。ミステリーは、内容が判ってしまうとつまらないので、ここでは書きませんが、世間が騒いでいるほどビックリすることはなかったと言うのが感想です。
何を深く追求するのかが気になって、話題の六本木ヒルズまで出かけたのですが、普通の絵画を見慣れているあさぎにとっては、ちょっとと思うところもたくさんありました。そうそう、入館料が高いのは場所代と割り切ることにした方が良さそうです。
展示内容は、ミステリーのキーポイントを動画とオブジェで構成しています。動画には、液晶テレビとプロジェクションが使われていて、なんとなく未来的な感じがしました。将来、絵画のオリジナルがなくなってしまったときとか、遠隔地で鑑賞するする場合にこんな形になるのかなと思ったりしました。
しかしというか、当然というか、オリジナルとはぜんぜん違います。まず、作品自体の存在感がいまひとつであること(たぶん、コントラストと質感の問題と思います)。鑑賞モードと解説モードがあっておもしろいのですが、大きなコンピュータ画面を見ているようでさみしい感じがします。
オリジナルに拘らないでインスタレーションのような展示をした方が良かったのではと思ってしまいます。作品は、アートではなく、インフォメーションなのだと思いました。デジタル社会の縮図のような気がします。
あまり良いとことがなかったのですが、ひとつだけ良かった作品がありました。それは、実物大の『最後の晩餐』のデジタル画像です。どう頑張ってもサンタ・マリア・デレ・グラーツィエ聖堂から持ってくることは不可能ですし、本物ではコントラストの問題もあって鮮明には見えないと思います。
大きさだけは、同じですからその迫力は伝わってきます。デジタルと言ううだけに綺麗です。ただ、文句があるとすれば、余計な解説や音楽は要らないので静かにゆっくり見せて欲しかったです。妙な演出で全体を台無しにしているように思いました。

レオナルド・ダ・ヴィンチ「最後の晩餐、1498」
※森アーツセンターギャラリー
※ダ・ヴィンチ・コード展
困難に打ち勝つ希望 ~ 陳進展 ― 2006年05月04日 10時57分22秒
松涛美術館がある周りは、大人の街である渋谷らしさが残っています。あさぎが過ごした学生時代の思い出の場所も近く、いつ訪れても雰囲気が良く好きな所です。子供ぽい駅前は、大嫌いですが・・。いつもの休日よりは、少ない人ごみにほっとしながら午後の渋谷にくりだしました。

陳進・・聞きなれない画家でした。名前から日本人ではないことが想像できたのですが、彼女の描く絵は日本人が求めてきた美しい世界でした。そして、彼女は、その美しい世界からは判らない激動の時代をかけ抜けぬけ、日本と台湾との間で苦悩をした人でした。
いまだに日本、台湾、そして中国の間ではいろいろな問題が解決しないままです。台湾は、1895年に日本の統治下に入り多くの日本文化が入ってくることになります。陳進は、その台湾に1907年に生まれ、日本から持ち込まれた日本画と出会います。
彼女は、才能を認められ日本に留学をすることになり、鏑木清方門下に学び1934年には帝展に入選するほどに実力をつけるのでした。しかし、彼女がまさに活躍をしようとした時代、日本は戦争へと突き進んで行きます。戦争の激化、敗戦、そして、彼女が中国人であるということは、彼女の人生を翻ろうすることに・・。
台湾に戻った彼女には、文化が衝突する渦に巻き込まれます。日本統治下からの開放は、画壇にも影響し日本画の排斥と伝統的中国画(水墨画)の復興の摩擦を生んでしまいます。しかし、彼女は、日本画の持つ繊細さを捨てず奥深い中国画を取り込むという方法で危機を乗り越えます。
今回の展覧会では、彼女の帝展入選前後の作品から台湾に戻り結婚、出産を経て晩年に至るまで作品を網羅しています。美人画、植物画、風景画といろいろはテーマに挑戦しています。初期の作品以外、あまり大きな作品はないのですが、彼女の人生を垣間見るようでおもしろいです。
やはり、目を引く作品は、帝展に入選した『合奏』でしょう。チャイナドレスの女性が2人、椅子に腰掛けて楽器を演奏しています。清楚な顔立ちは、さすがに鏑木清方一門です。モデルは、彼女の実姉とのことで裕福な家庭で育ったという貴賓が漂っています。

陳進「合奏、1934」
年を重ねるごとに困難を乗り越える力強さが作品から伝わってくるのが不思議です。多くの人たちが国や文化の板ばさみにあい生き抜いてきている中、彼女の明るさや未来に対する希望は、郡を抜き輝き見るものに勇気を与えてくれるようです。
※渋谷区立松涛美術館

陳進・・聞きなれない画家でした。名前から日本人ではないことが想像できたのですが、彼女の描く絵は日本人が求めてきた美しい世界でした。そして、彼女は、その美しい世界からは判らない激動の時代をかけ抜けぬけ、日本と台湾との間で苦悩をした人でした。
いまだに日本、台湾、そして中国の間ではいろいろな問題が解決しないままです。台湾は、1895年に日本の統治下に入り多くの日本文化が入ってくることになります。陳進は、その台湾に1907年に生まれ、日本から持ち込まれた日本画と出会います。
彼女は、才能を認められ日本に留学をすることになり、鏑木清方門下に学び1934年には帝展に入選するほどに実力をつけるのでした。しかし、彼女がまさに活躍をしようとした時代、日本は戦争へと突き進んで行きます。戦争の激化、敗戦、そして、彼女が中国人であるということは、彼女の人生を翻ろうすることに・・。
台湾に戻った彼女には、文化が衝突する渦に巻き込まれます。日本統治下からの開放は、画壇にも影響し日本画の排斥と伝統的中国画(水墨画)の復興の摩擦を生んでしまいます。しかし、彼女は、日本画の持つ繊細さを捨てず奥深い中国画を取り込むという方法で危機を乗り越えます。
今回の展覧会では、彼女の帝展入選前後の作品から台湾に戻り結婚、出産を経て晩年に至るまで作品を網羅しています。美人画、植物画、風景画といろいろはテーマに挑戦しています。初期の作品以外、あまり大きな作品はないのですが、彼女の人生を垣間見るようでおもしろいです。
やはり、目を引く作品は、帝展に入選した『合奏』でしょう。チャイナドレスの女性が2人、椅子に腰掛けて楽器を演奏しています。清楚な顔立ちは、さすがに鏑木清方一門です。モデルは、彼女の実姉とのことで裕福な家庭で育ったという貴賓が漂っています。

陳進「合奏、1934」
年を重ねるごとに困難を乗り越える力強さが作品から伝わってくるのが不思議です。多くの人たちが国や文化の板ばさみにあい生き抜いてきている中、彼女の明るさや未来に対する希望は、郡を抜き輝き見るものに勇気を与えてくれるようです。
※渋谷区立松涛美術館
騙されるな! ~ マルク・シャガール ラ・フォンテーヌの寓話 ― 2006年05月05日 21時59分20秒
美しい庭園に囲まれた美しい美術館という印象が、美術雑誌や書籍から感じいて一度訪れてみたかった美術館のひとつでした。しかし、あまりにも遠い場所にあるので、そう簡単には行くことができません。成田空港の手前にあって、横浜からは1時間半以上もかかります。

手入れの整えられた芝生、花をつけた草花たちの中に中世を思わせる建物が現われます。暖かいこの日は、とても気持ち良く「わざわざ遠いところを・・」と歓迎されているようでした。美術館の前には白鳥がいる池があって、大好きな人と一緒に散歩ができたらと思いつつ館内に入って行きました。
美術館は、1階と2階に展示室がありました。そして、おもしろいことにこの美術館では、常設展示の作品から鑑賞をするようになっていて、企画展があとにあるという構成で少し変な感じがしました。だから、はじめ鑑賞コースを間違えたかと思ってしまい、1階から2階に上がって企画展になったときには「あれれ・・」といった感じになりました。
常設展示には、印象派、エコールド・パリなど海外の作品の他に日本画や曼荼羅のような東洋的な作品まで幅広いコレクションが見ることができます。ただ、ひとつひとつの作品は、素晴らしいのですが連続して見た時に少しまとまりがないようにも感じました。たぶん、コレクターの趣味の問題だと思いますが・・。
さて、企画展の「ラ・フォンテーヌの寓話」ですが、マルク・シャガールの版画中心に展示がされていました。ラ・フォンテーヌとは、中世のフランス文学者で、その作品は、フランスではとても人気があるそうです。寓話は、イッソプ寓話をベースにして各国の民話などを取りいれ書かれているそうです。
その内容は、子供には難しいともいわれていますが、大人にとってはさまざまな教訓がありおもしろそうです。この寓話は、過去に多くの画家が挿絵を作成していたのそうですが、展覧会では、画商ヴォラールがシャガールに挿絵の依頼したものがメインになっています。
銅板で刷られた版画にポイントなる部分に色をおいていく手法が使われることで、作品にどことなく温かみが与えているように思います。寓話の挿絵なのでその場面の前後には、物語があります。例えは、展覧会のポスターにもなっている『カラスとキツネ』の話しは、こんな感じです。

マルク・シャガール「カラスとキツネ、1930」
カラスが、くちばしにチーズをくわえて木の枝にとまっています。そこにキツネが現われカラスを見上げて、「こんにちは、カラスの旦那。旦那はなんて立派なんだ。その羽は実に見事でこの森に並ぶものなどいない。旦那の声も威厳があるのだろうね。ぜひ、そのすばらし声を聞かせてくれないだろうか?」と言いました。
これにカラスは、有頂天になって喜び思わず声を出してしました。すると、くちばしからチーズが落ちてしまいました。すかさずキツネは、チーズを拾い食べてしまします。そして、キツネは唖然とするカラスに言うのでした。
「ご親切なカラスの旦那、ひとつ覚えておくといい。お世辞をいう者は、それをに耳を貸すもののおかげで生きているんだよ。この教訓は、チーズひとかけらの価値があるだろう。」、これにカラスは、我にかえって騙されたことに気がつくのですが、すでに遅かったということです。
全部の作品に解説があるわけではないのですが、人間の愚かさや教訓の一場面が挿絵として描かれいると思うと楽しいです。また、シャガールというとカラフルな作品しか知らなかったのですが、銅板のモノトーンの世界もまた味わいがあって良いものです。
フランスでは、はじめシャガールをロシアからの異国人として自国の寓話を描くことを拒絶されたそうです。しかし、彼の独自の世界は人々の心を掴む魅力があったため、徐々に認められるようになったようです。この話も寓話のようでなんだかおかしい話しであるように思えるのが不思議です。
※川村記念美術館

手入れの整えられた芝生、花をつけた草花たちの中に中世を思わせる建物が現われます。暖かいこの日は、とても気持ち良く「わざわざ遠いところを・・」と歓迎されているようでした。美術館の前には白鳥がいる池があって、大好きな人と一緒に散歩ができたらと思いつつ館内に入って行きました。
美術館は、1階と2階に展示室がありました。そして、おもしろいことにこの美術館では、常設展示の作品から鑑賞をするようになっていて、企画展があとにあるという構成で少し変な感じがしました。だから、はじめ鑑賞コースを間違えたかと思ってしまい、1階から2階に上がって企画展になったときには「あれれ・・」といった感じになりました。
常設展示には、印象派、エコールド・パリなど海外の作品の他に日本画や曼荼羅のような東洋的な作品まで幅広いコレクションが見ることができます。ただ、ひとつひとつの作品は、素晴らしいのですが連続して見た時に少しまとまりがないようにも感じました。たぶん、コレクターの趣味の問題だと思いますが・・。
さて、企画展の「ラ・フォンテーヌの寓話」ですが、マルク・シャガールの版画中心に展示がされていました。ラ・フォンテーヌとは、中世のフランス文学者で、その作品は、フランスではとても人気があるそうです。寓話は、イッソプ寓話をベースにして各国の民話などを取りいれ書かれているそうです。
その内容は、子供には難しいともいわれていますが、大人にとってはさまざまな教訓がありおもしろそうです。この寓話は、過去に多くの画家が挿絵を作成していたのそうですが、展覧会では、画商ヴォラールがシャガールに挿絵の依頼したものがメインになっています。
銅板で刷られた版画にポイントなる部分に色をおいていく手法が使われることで、作品にどことなく温かみが与えているように思います。寓話の挿絵なのでその場面の前後には、物語があります。例えは、展覧会のポスターにもなっている『カラスとキツネ』の話しは、こんな感じです。

マルク・シャガール「カラスとキツネ、1930」
カラスが、くちばしにチーズをくわえて木の枝にとまっています。そこにキツネが現われカラスを見上げて、「こんにちは、カラスの旦那。旦那はなんて立派なんだ。その羽は実に見事でこの森に並ぶものなどいない。旦那の声も威厳があるのだろうね。ぜひ、そのすばらし声を聞かせてくれないだろうか?」と言いました。
これにカラスは、有頂天になって喜び思わず声を出してしました。すると、くちばしからチーズが落ちてしまいました。すかさずキツネは、チーズを拾い食べてしまします。そして、キツネは唖然とするカラスに言うのでした。
「ご親切なカラスの旦那、ひとつ覚えておくといい。お世辞をいう者は、それをに耳を貸すもののおかげで生きているんだよ。この教訓は、チーズひとかけらの価値があるだろう。」、これにカラスは、我にかえって騙されたことに気がつくのですが、すでに遅かったということです。
全部の作品に解説があるわけではないのですが、人間の愚かさや教訓の一場面が挿絵として描かれいると思うと楽しいです。また、シャガールというとカラフルな作品しか知らなかったのですが、銅板のモノトーンの世界もまた味わいがあって良いものです。
フランスでは、はじめシャガールをロシアからの異国人として自国の寓話を描くことを拒絶されたそうです。しかし、彼の独自の世界は人々の心を掴む魅力があったため、徐々に認められるようになったようです。この話も寓話のようでなんだかおかしい話しであるように思えるのが不思議です。
※川村記念美術館





